| 目次 |
|---|
地方創生カレッジプログラム「初級地域公共政策士」の3つの特徴
- eラーニング受講で初級地域公共政策士資格に必要なポイントが取得できます
- 地域公共政策士として求められる能力(課題発見力・課題共有力・課題分析力)が身につきます
- 全国から注目を集める京都の先進的取り組み事例を学べます
地方創生カレッジとは?
内閣府の「地方創生人材プラン」に基づいて開講されるeラーニング講座です。
持続可能な地域社会をつくるための人材を育成・確保するため、実践的な知識を提供するほか、必要に応じて実地研修も効果的に取り入れています。
「地方創生カレッジ」の資格取得のための対象科目は下記12科目です。
ご確認お願いいたします。
日本生産性本部が提供されている、地方創生カレッジeラーニング講座の全ての講座が対象ではありません。
下記12科目の対象科目以外を修了されましても、資格取得の対象科目とはなりませんのでご注意ください。
(1科目1ポイントですので、10科目修了いただければ結構です。)
| 014 | 非営利組織の理論と実績 | 深尾昌峰 |
|---|---|---|
| 019 | 都市の現代的振興論 | 矢作 弘 |
| 009 | 公共政策学の基礎 | 新川達郎 |
| 013 | 文化経済・文化政策論 | 阪本 崇 |
| 016 | 地域課題解決に果たす企業の役割 | 三浦 潔 |
| 018 | 地域農業の再生・創生 | 矢口芳生 |
| 012 | 共生の社会学 | 大束貢生 |
| 010 | 政策づくり入門:よい政策がわかる よい事業がつくれる | 窪田好男 |
| 020 | 公民協働におけるファシリテーション技法 | 青山公三 |
| 017 | 地域に飛び出す公務員 | 山崎仁士 |
| 011 | 地域課題と法政策 | 中谷真憲 |
| 015 | 地方創生における教育の役割と可能性 | 高見 茂 他 |
(頭の数字は、日本生産性本部 地方創生カレッジ eラーニング講座の番号)
資格取得の流れ
地方創生カレッジプログラムの受講から資格取得の流れは下記の通りです。
地方創生カレッジプログラム(初級)
①e-learning(地方創生カレッジプログラム)を修了(上記12科目の内10科目=10ポイント取得)し、その修了証をもって
②アクティブ・ラーニング科目にお申込みいただきます。
①②の並行受講は原則できません。
「地方創生カレッジプログラム」の受講料については、
①のe-learningは無料です。
②のアクティブ・ラーニングは、受講料が22,000円(税込み)です。
②については実施場所によっては、別途費用がかかるかもしれませんので、詳細については、実施団体のグローカル人材開発センターへお問い合わせください。
特定非営利活動法人グローカル人材開発センター
〒602-8061 京都市上京区油小路通中立売西入ル甲斐守町97番地 西陣産業創造会館(旧西陣電話局)2階
Tel:075-411-5010
Fax:075-411-5011
Mail: info@glocalcenter.jp
https://glocalcenter.jp/
①②2つを修了いただき、それぞれの修了証と資格申請書を当機構(地域公共人材開発機構)へご提出ください。
資格申請手数料(3,300円)をお振込みいただき、資格取得となります。
講座一覧
| 科目名 | 非営利組織の理論と実績 |
|---|---|
| 講師 | 深尾 昌峰(龍谷大学政策学部 准教授)他 |
| 内容 | 本講座は、日本の非営利組織の発展を目指す観点から、非営利組織の理論的背景、現実的意義、これまでの到達について、系統的に学習できるように構成されています。 |
| 科目名 | 都市の現代的振興論 |
|---|---|
| 講師 | 矢作 弘(龍谷大学政策学部 教授)他 |
| 内容 | 20 世紀後半~最近までの先進諸国の都市事情(欧米の都市)、都市計画制度、アーバンデザインに関する動向について知り、わが国の地方都市の持続可能性について考える講義です。 |
| 科目名 | 公共政策学の基礎 |
|---|---|
| 講師 | 新川 達郎(同志社大学政策学部 教授)他 |
| 内容 | この講座では、公共政策学を学ぶ上で必要とされる基礎的な知識を習得することができます。講座を通じて、公共政策学の基本的なトピックを全般的に学ぶことができます。 |
| 科目名 | 文化経済・文化政策論 |
|---|---|
| 講師 | 阪本 崇(京都橘大学現代ビジネス学部 教授)他 |
| 内容 | 芸術や文化遺産をはじめとして、文化の生産・消費の経済的特徴、公的支援の根拠と方法を学んだ上で、具体的事例として京都の観光政策、文化財政策について取り上げます。 |
| 科目名 | 地域課題解決に果たす企業の役割 |
|---|---|
| 講師 | 三浦 潔(京都文教大学総合社会学部 教授) |
| 内容 | この講座では、企業に関する基礎的な知識を学び、京都の企業が取り組む地域課題解決の事例を通して、今日の地域課題解決の担い手としての企業の役割について考えます。 |
| 科目名 | 地域農業の再生・創生 |
|---|---|
| 講師 | 矢口 芳生(福知山公立大学地域経営学部 教授)他 |
| 内容 | 地域農業の課題やその対応事例を学習します。前半4回の講義では、総論として地域農業に関する理論を、後半3回の講義では、農業の6次産業化、エコツーリズム等の各事例を紹介します。 |
| 科目名 | 共生の社会学生 |
|---|---|
| 講師 | 大束 貢生(佛教大学社会学部 准教授) |
| 内容 | 「身分制社会」や「貴賤による差別」「競争社会」「能力による抑圧・排除の正当化」を通して、共生社会は可能なのかについて学びます。 |
| 科目名 | 政策づくり入門 -よい政策が分かる よい事業がつくれる- |
|---|---|
| 講師 | 窪田 好男(京都府立大学公共政策学部 教授) |
| 内容 | よい政策をつくるために必要な4要素(目的、調査、手法、実現)を学ぶことで、政策づくりに必要な能力を習得します。 |
| 科目名 | 公民協働におけるファシリテーション技法 |
|---|---|
| 講師 | 青山 公三(龍谷大学政策学部 教授)他 |
| 内容 | 公務員が公民協働を進めるにあたって必要なファシリテーションの技法を習得することができます。 |
| 科目名 | 地域に飛び出す公務員 |
|---|---|
| 講師 | 山崎 仁士(NPO法人自治創出プラットフォーム 京都もやいなおしの会 理事長)他 |
| 内容 | 様々な公務員の事例を知り、これからの公務員に必要な姿勢・考え方を学ぶことができます。 |
| 科目名 | 地域課題と法政策 |
|---|---|
| 講師 | 中谷 真憲(京都産業大学法学部・世界問題研究所 教授)他 |
| 内容 | 地域の課題を考える際に必要な公共政策的な視点についての紹介を踏まえ、自治体改革や地域協働、少子高齢化、地域と社会安全という個別課題を解決するための法政策について学びます。 |
| 科目名 | 地方創生における教育の役割と可能性 |
|---|---|
| 講師 | 高見 茂(京都大学大学院教育学研究科・教育学部 教授)他 |
| 内容 | 地域における教育の役割について、国内外の事例を参照しながら、その理論や枠組みについて学びます。 |
京都アライアンスとは
京都府内の大学・自治体・NPO・経済団体等でつくる地域公共人材養成のためのプロジェクトチームです。地方創生カレッジでの講座提供もプロジェクトの一つです。
Kyoto Allianceメンバーがその特徴を活かした講座を提供します。

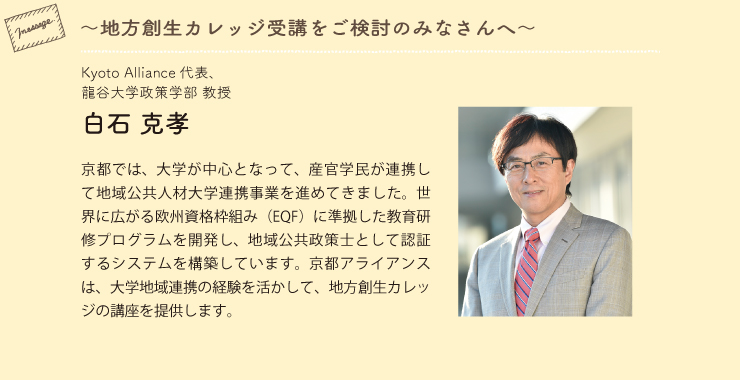
地方創生カレッジプログラムとLORC
有効な教育・研修プログラムには教育3要素の有機的な統合が不可欠です。教育の3要素とは知識(Knowledge)、技法(Skills)、態度(Attitude)をいい、その頭文字をとってKSAと表現されます。「地域公共政策士」プログラムでは講義という座学(e-ラーニング講座はこれに当たります)によってKSの修得を図り、フィールドという現場でのCBL(Community Based Learning)やPBL(Project Based Learning)によるアクティブ・ラーニングを通じてAの獲得を狙っています。通常の日本の高等教育ではKSに焦点を当てていましたが、KSとAの統合を図っているのが、この教育プログラムの特徴です。
教育構造としてはシンプルですが、ここに到達するまでには15年近くの4ステップにわたる研究蓄積が必要でした。第1のステップは文部科学省私学研究高度化事業「地域における公共政策と人的資源の開発システムの研究」(2003年~2007年)でした。この研究連携の軸となったのが、龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)でした。ここでの成果はその後の原点となっています。その原点は以下の3つに要約されます。
- 現代社会では、「公共」の内実が構造的な基本的変動を起こしているという時代認識です。従来「公共」は政府のサービスの範疇でしたが、社会の成長は「より広い多様な公共サービス」を求め、同時に、財政的な制約からも「より効率的な政府」を求めています。これは、政府の在り方の地殻変動を意味するとともに、公共の定義の見直しを意味しているのです。
- この公共の定義にみる地殻的変動は、好況を担うのが政府だけではなく、多様な主体(関係者)による社会への転換の必要性を意味しています。多様な主体が重層的に連携しながら公共を創り出す柔軟なオープンな社会の形成を必要としているのです。公共を担う主体の多様化が実現する社会を創り出さねばなりません。
- 公共が多様な主体による重層的連携によって実現する社会とは、政策決定やそれに基づく政策実施の構造も基本的に変化することを意味します。従来のように、公共の内実を形作る政策が政府で決定され、中央(政府)から現場への縦の関係で実施される垂直統合を軸とする構造でなく、各種の関係主体が横に連携して政策の意思決定を図り、政策の実施にあたる水平統合を軸とする社会への転換が必要となり、参加型政策形成が不可欠となります。
第2~第4ステップは、理念的枠組の原点に基づいて、現実に有効性のある制度システムの構築に取り組みました。理念の構築に留まらず。それを現実的なシステム構築に結びつけたのが、一連の研究蓄積の特徴です。第2のステップは、文部科学省戦略的大学連携支援事業「地域公共人材のための京都府内における教育・研修プログラムと地域資格認証制度の開発」(2008年~2010年)でした。LORCで築き上げられた原点を実際に生かす教育プログラムの構築と、そこで育った人材を社会的に蓄積育成度として資格認証制度を構築することが目的でした。その具体的な成果がCOLPUです。第3のステップは、文部科学省大学間連携共同教育推進事業(地学連携)「地域資格制度による組織的な大学地域連携の構築と教育の現代化」(2012年~2016年)でした。その具体的な成果が一般社団法人京都府北部地域・大学連携機構CUANKAです。第4のステップは、文部科学省大学間連携共同教育推進事業(産学連携)「地域資格制度による組織的な大学地域連携の構築と教育の現代化」(2012年~2016年)でした。その具体的な成果がNPO法人グローカル人材開発センターです。
「地域公共政策士」プログラムは、基本的には大学内の高等教育をいかに現実社会で有効性を持つものにするかの問題意識の下に展開されてきました。これを地方創生かレジとして社会人に対しても開放に踏み切ったことは、単に高等教育内のシステム展開に留まらず、今日の日本の置かれた社会状況を変革させる意味を持つものと認識しています。現代日本は100歳時代と言われるように高齢化社会の最先端を行ってます。これを前提に、社会をどう持続的に発展させていくかを考えなければならない段階に来ています。このことは、生涯教育の重要性が増してきたことを意味しますが、従来の生涯教育は、一般教養の普及により労働力の質的底上げでしたが、今さらに積極化しなければならないのは、専門性を再構築による人材の育成です。教養を軸とした教養人の育成とともに職能を軸とした専門家の再教育(リカレント教育)がこれからの生涯教育にとって非常に重要となります。地方創生カレッジとして「地域公共政策士」プログラムを実施することは、大学がこの社会的役割を担っていくとの方向性を示すものと言えます。


